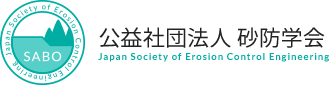「砂防の観測の現場を訪ねて1~土砂災害を知るための観測~」の発刊について
気候の変動が世界的に顕著になってきており,1990年代以降,日本でも深刻な土砂災害が頻発するようになりました。このような土砂災害を防ぐためには,これから発生するであろう土砂災害を適切に予測・想定して来るべき未来に備える必要があり,そのためには,土砂の移動現象やこれに伴う災害の発生機構に対する理解と洞察が不可欠です。そして,正しく理解し,より深く洞察するためには,現場で直接データを取る現地観測を継続的に実施することが重要です。
このたび,地道ではあるものの土砂災害研究や対策実施において必要不可欠であるこれら現地調査や観測の重要性や面白さを広く伝えることを目的とし,砂防学会誌「観測の現場を訪ねて」に掲載された記事を改めて再編のうえ「砂防の観測の現場を訪ねて」として発刊いたしました。第1巻となる本書では,土砂災害そのものを「知る」ための観測をテーマとし,土砂災害発生のメカニズムや原因分析,さらには将来の発生予測なども含め,現地での詳細な調査や観測により,これらの解明に果敢に取組んだ事例を紹介しています。
ぜひ一度本書を手に取っていただき,日々の研究や業務の参考にして頂くとともに,「砂防」や「土砂災害」に関心ある方へ広くご紹介を頂けましたら幸いです。
第1編 土砂災害がどのようにして発生したかを知るために観測する
第1章 1993 年鹿児島県土石流災害
<シラス台地周辺の大規模な土砂災害はどのようにしておこるのか>
第2章 1999 年広島県土石流災害
<同時多発する表層崩壊はどのようにしておこるのか>
第3章 1999 年以降の三重県藤原岳の土石流
<1つの場所で何度も発生する土石流はどのようにしておこるのか>
第4章 2005 年宮崎県の土砂災害
<深層崩壊による土砂災害はどのようにしておこるのか>
第5章 2013 年伊豆大島土石流災害
<火山地域の表層崩壊による土砂災害はどのようにしておこるのか>
第2編 被害の拡大を防ぐために観測する
第6章 1990 年雲仙・普賢岳の噴火
<土石流や溶岩ドーム崩落による被害を防ぐために>
第7章 2000 年三宅島の噴火
<早期緑化・復興のために>
第8章 2008 年岩手・宮城内陸地震
<融雪に起因した土砂災害の減災を目指して>
第3編 土砂災害の発生を予測するために観測する
第9章 土石流の発生・流下を予測する
<不安定土砂の蓄積状況から土石流を考える>
第10 章 表層崩壊の発生を予測する
<地中の脆弱層を把握する>
第11章 斜面崩壊の発生を予測する
<世界文化遺産を守る>
第12章 深層崩壊の発生を予測する
<地下水の集中箇所を把握する>
ボックスのコンテンツ
購入申し込み方法
必要事項を記入の上、送信してください。
メール送信後に下記まで代金2,200円/冊(税込み)をお振込みください。振込が確認されましたら、順次本書を送付いたします。なお、令和2年8月までにお申し込み頂いた場合には、送料無料といたします。
(口座名義:公益社団法人砂防学会)
*「砂防の観測の現場を訪ねて1」のちらしはこちら